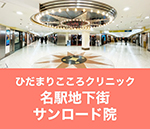名古屋駅徒歩0分
大人のための
メンタルクリニック
診療案内
認知症認知症
認知症とは
認知症は、脳の機能が徐々に低下し、記憶や思考、判断力、社会的行動などの認知機能が持続的に障害される状態を指します。加齢に伴う単なる物忘れとは異なり、日常生活に支障をきたすレベルの障害が特徴です。
医学的には、認知症はさまざまな疾患や障害が原因となって引き起こされる「症候群」として分類されます。

認知症の主な原因と種類
認知症にはいくつかの主要なタイプが存在し、それぞれ異なる病態生理が関わっています。
① アルツハイマー型認知症
最も多いタイプで、全認知症の約60〜70%を占めます。脳内に「アミロイドβ」と「タウたんぱく」という異常なたんぱく質が蓄積し、神経細胞が変性・死滅することで発症します。初期症状としては短期記憶障害(直近の出来事を忘れる)が目立ち、進行するにつれて言語障害や見当識障害、遂行機能障害が現れます。
② 血管性認知症
脳梗塞や脳出血などによる脳血管障害が原因となるタイプです。脳の血流が途絶えることで神経細胞が壊死し、認知機能が損なわれます。症状は「まだら認知症」と呼ばれるように、障害される機能にばらつきが見られるのが特徴です。また、情動失禁(感情が抑えられず涙や笑いが出る)や歩行障害も伴うことがあります。
③ レビー小体型認知症
レビー小体という異常なたんぱく質が大脳皮質や脳幹に蓄積することで発症します。特徴的な症状として、鮮明な幻視(例:動物や人物が見える)、認知機能の変動(注意力や覚醒度が日によって変わる)、パーキンソン症状(手足の震えや筋固縮)が挙げられます。アルツハイマー型とは異なり、記憶障害は初期には目立たないことが多いです。
④ 前頭側頭型認知症
前頭葉や側頭葉の萎縮を伴う認知症で、比較的若い年代(50〜60代)に発症しやすいのが特徴です。初期には記憶障害よりも性格や行動の変化が目立ちます。例えば、衝動的な行動、無関心、反社会的行動、常同行動(同じ行動を繰り返す)などが現れることがあります。言語障害が中心となるタイプも存在します。

認知症の症状の進行
認知症は、進行度に応じて症状が変化していきます。
【初期症状】
- 物忘れが増え、特に最近の出来事を思い出せない
- 同じ質問や話を繰り返す
- 慣れた場所で道に迷う
- 意欲や関心の低下
【中期症状】
- 名前や顔を忘れる
- 時間や場所の感覚が混乱する
- 服を着替えたり、料理をするなどの手順が分からなくなる
- 感情のコントロールが難しくなる(怒りっぽい、泣きやすいなど)
【後期症状】
- 言葉がほとんど出なくなる
- 自力での食事や排泄が難しくなる
- 寝たきりになることもある
- 周囲への反応がほとんどなくなる

認知症の中核症状と周辺症状(BPSD)
認知症の症状には、大きく分けて「中核症状」と「周辺症状(BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)」があります。
中核症状
中核症状は、脳の神経細胞が直接的に損傷を受けることで起こる基本的な症状で、認知症の種類を問わず共通して見られるものです。
- 記憶障害:新しいことを覚えられない、昔の記憶も失われる
- 見当識障害:時間や場所、人がわからなくなる
- 理解・判断力の低下:状況を理解したり、判断する力が低下する
- 実行機能障害:計画を立てたり、手順を踏んで行動することが難しくなる
- 失語:言葉が出てこなくなる、話しても意味が伝わらない
- 失行:体の動かし方がわからなくなる(服を着る、道具を使うなど)
- 失認:見えているものが何なのか認識できない
周辺症状(BPSD)
周辺症状は、中核症状に伴って現れる心理的・行動的な症状で、本人の性格や環境によっても大きく影響を受けます。
- 幻覚・妄想:存在しないものが見えたり、誰かが悪意を持っていると疑ったりする
- 興奮・暴力行為:怒りやすくなり、大声を出したり暴力的になる
- 抑うつ:気分が落ち込み、無気力になる
- 徘徊:目的もなく歩き回ったり、外に出て迷子になる
- 睡眠障害:昼夜逆転や夜間の覚醒が増える
- 拒絶・抵抗:食事や入浴、服薬などを強く拒否する
これらの周辺症状は、本人の不安や混乱、環境の変化などが引き金となることが多く、薬物療法や非薬物療法(環境調整、心理的支援など)を組み合わせた対応が重要です。

認知症の診断
認知症の診断には、以下の方法が組み合わされます。
- 問診・症状の観察➡家族や本人への聞き取りを行い、症状の進行や影響を確認します。
- 認知機能検査➡MMSE(Mini-Mental State Examination)や長谷川式簡易知能評価スケールなどを用いて、記憶力や見当識、計算力などを評価します。
- 画像診断➡CTやMRIで脳の萎縮や血管障害を確認します。PET検査ではアミロイドβの蓄積状況を評価できます。
- 血液検査➡ビタミン不足や甲状腺機能異常など、他の疾患による認知障害を除外します。
治療とケアについて
現時点では認知症を完全に治す治療法は確立されていませんが、症状を遅らせたり、生活の質を向上させる治療やケアが重要です。
【薬物療法】
- コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル、リバスチグミン、ガランタミン)➡アセチルコリンという神経伝達物質の分解を抑え、記憶や認知機能を維持します。
- NMDA受容体拮抗薬(メマンチン)➡過剰なグルタミン酸の働きを抑え、神経細胞の損傷を軽減します。
- 抗精神病薬や抗うつ薬➡興奮や抑うつ、不眠などの周辺症状(BPSD)に対して必要に応じて使用されます。
【非薬物療法】
- 認知リハビリテーション➡記憶や注意力を刺激する作業療法や回想法を取り入れます。
- 環境調整➡混乱を防ぐために住環境を整備し、安全対策を行います。
- 家族支援➡介護負担を軽減するために、介護サービスやカウンセリングを活用します。

まとめ

よくあるご質問
認知症を予防するための治療などは可能ですか?
認知症の薬には、完全ではありませんが、予防や進行を遅らせる効果があるとされています
過去に生活習慣病を発症している方は、認知症になる可能性が高いと言われているので、高血圧や高脂血症などの日々の治療も重要ですし、認知症に対するお薬も進行を遅らせる効果があるとされています。
高齢者ではなくても認知症になる可能性はありますか?
若年性認知症という病気もあります。
認知症は脳の神経細胞が破壊され、脳の知的機能が低下し、日常生活を送ることが困難になる症状をいいます。脳の神経細胞が破壊されてしまう原因については、病気も含めて複数あり、高齢者だけではなく若くても発症する可能性があります。
イライラなどによる問題行動を抑えることはできますか?
はい、薬による治療で抑えることができます
現在、認知症そのものを完全に治しきる薬というのはまだありませんが、内服により進行を遅らせたり、一部症状を改善したりすることは可能と言われています。
特に、認知症の周辺症状である、イライラなどによる問題行動、幻覚や妄想、興奮を抑える効果があるとされています。
認知症の分類で、それぞれどんな症状がありますか?
症状により、大きく分けて4つに分類することができます
<アルツハイマー病>
アルツハイマー病は全認知症の半分以上をしめる認知症の中でも代表的な疾患です。 生活面では、「言いたい言葉が出てこない」、「やる気がない」、あるいは慎重さや注意不足が現れます。次の時期には記憶障害は明らかになり、他人の言う事を理解するのが難しくなります。
<血管性認知症>
脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の血管が壊れる、くも膜下出血などの脳出血などの明らかな脳血管障害が起きたあと、 認知機能が低下した場合、血管性認知症といいます。脳の血管へのダメージは、高血圧や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病と密接に関連しているといわれています。
<レビー小体型認知症>
レビー小体型認知症は、もの忘れのほか、時間や場所がわからなくなったり、だんだんと身の回りのことができなくなるなどの症状が見られる認知症です。
<前頭葉側頭葉変性症>
前頭側頭葉変性症は、脳の前頭葉や側頭葉の委縮がみられる症状が発症する認知症です。アルツハイマー型が頭頂葉や側頭葉・内側の委縮が起こるのに対して、前頭側頭葉変性症は前頭葉や側頭葉に委縮が現れます。
2025.03.142025.03.15
診療案内
パニック症
一人で悩まずに、まずは一度ご相談ください
一人で悩まずに、
まずは一度ご相談ください

たくさんの方が
悩みを抱えて来院されています。
ご紹介している症状以外でも、「こんなことで受診していいのかな…」 と迷ったらまずは一度お気軽にお電話ください。